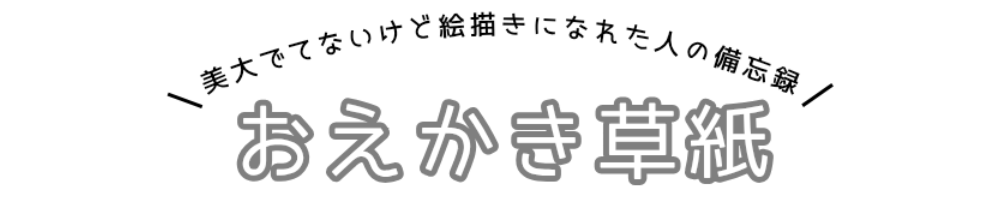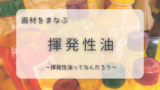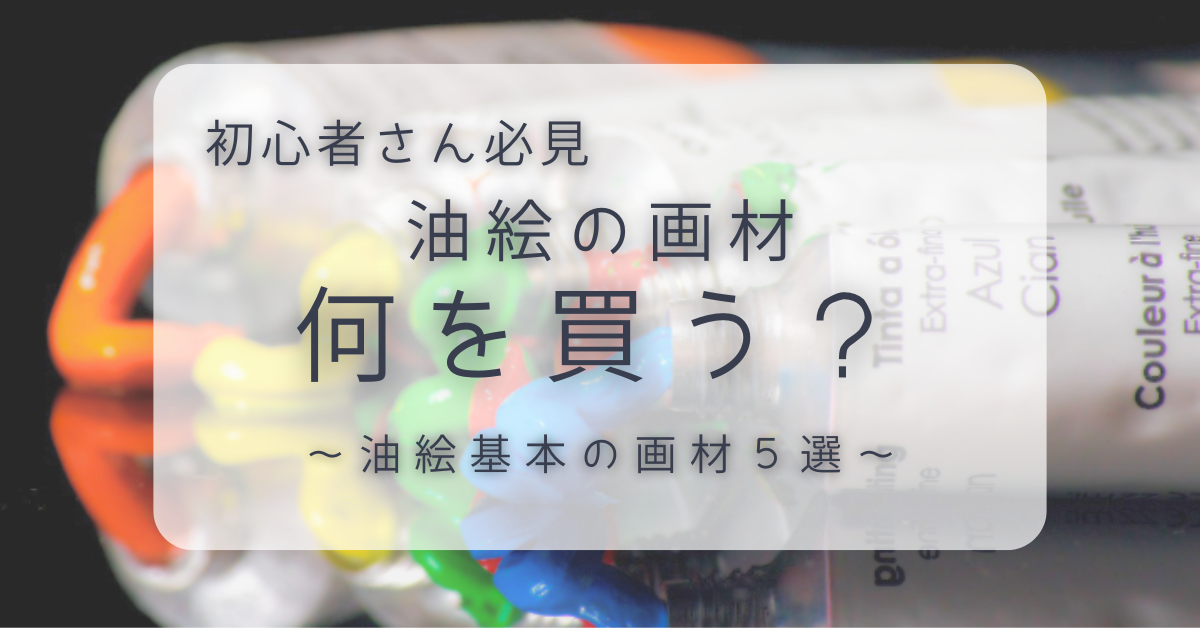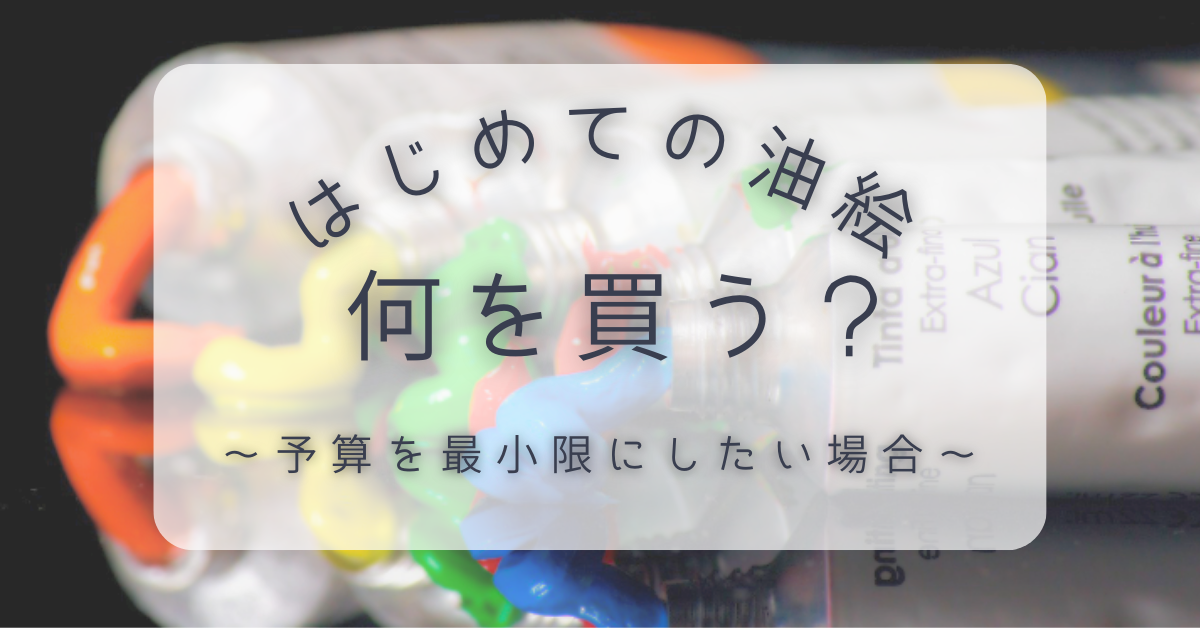『おえかき草紙』へようこそ!
管理人の もげら です。
こんにちは!
突然ですが、この記事にたどりついてくれたあなたに質問です。
「油絵を描いてみたいけど、あの独特なにおいが苦手・・・」
このように感じたこと、ありませんか?

あるある!あるで~!
油絵の魅力は、重厚感のある表現と、納得いくまでじっくり描けることだと思います。
その反面、画材のにおいが気になって、制作をためらう人も正直多いです。

においと片付けの手間がネックやな。
自宅のアトリエや賃貸マンションなどの密閉された空間で描く人にとって、この「におい問題」は深刻な悩みになると思います。
この記事では、油絵を描く時に発生する「におい」の原因にフォーカスをあてて、快適に制作できる環境をつくるための実践方法についてご紹介していきます◎
油絵のにおいを抑える2つの方法【初心者向け】

今回管理人が考えたにおいを抑える方法は、大きく分けて2パターンです。
- 換気や空気の流れを意識した制作スペースの工夫
- 市販されている無臭・低臭の画材(溶剤・乾性油・メディウムなど)を使う

環境を整える
画材は無臭でそろえる
・・・っちゅーことやな。
上記2つを意識すれば、「油絵は描きたいけどにおいがどうしてもダメ!」という方も、においを抑えて油絵を楽しむ方法が見つかるはずです◎
油絵のにおいが強くなる理由
油絵のにおいの主な原因は、画材に含まれる揮発性成分です。
例えば、テレピン・ペトロールなどの揮発性油です。
リンシードオイルなどの乾性油は、乾燥していく過程で独特なにおいを放ちます。

半乾き状態の時が最もにおいが強い傾向にあります。
揮発性油についてまとめた記事はコチラです
揮発性有機化合物(VOC)とは?
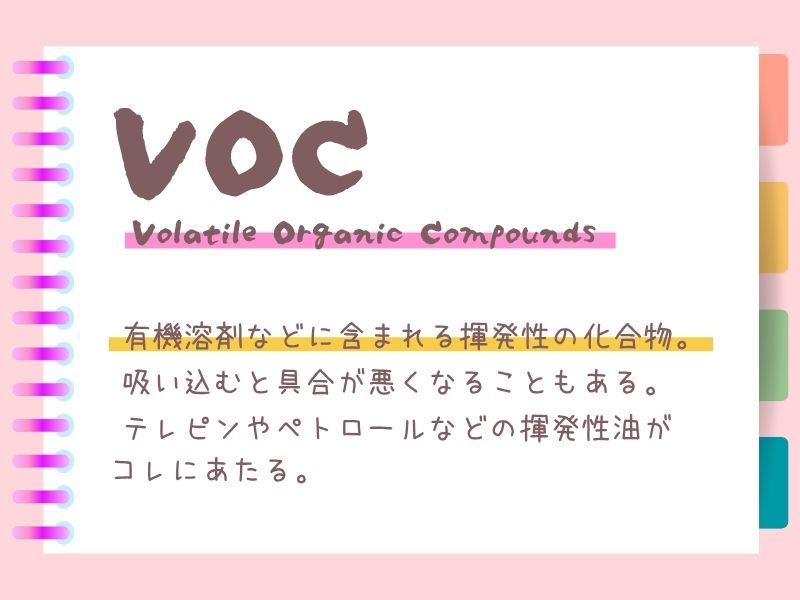
VOC(Volatile Organic Compounds)は、有機溶剤などに含まれる揮発性の化合物です。
油絵画材では、以下のような画材がVOCとして問題視されています。
- テレピン(植物性溶剤/においが強い)
- ペトロール(石油系溶剤/比較的においは弱め)
- ストリッパー(扱いに特に注意が必要)
- テレピンやぺトロールを含む調合オイル類
VOCは、空気中に放出されることでにおいの元になるだけではありません。
長時間吸い続けると、頭痛や倦怠感の原因になることもあるんです。
更に、発火する可能性もあります。
使用環境には十分注意が必要です。

閉め切った部屋の中で
ストリッパーを多量に使って具合が悪くなり
救急車で運ばれた人がいる・・・という
噂を聞いたことがあります。

閉め切り、ダメ!絶対!!
においを抑える換気の方法
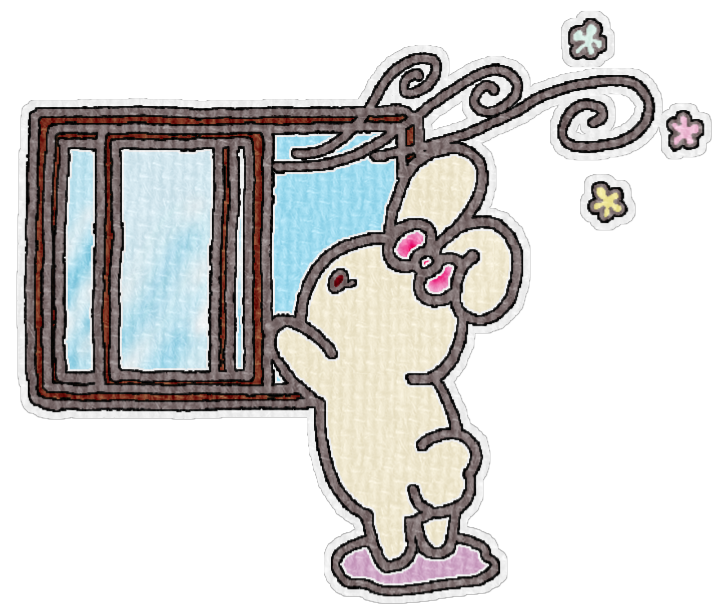
ここからは、「におい」にのみ焦点を当てていきます。
におい対策の基本は、とにかく空気をこもらせないことです。
特に室内で制作する場合は、換気の工夫がとても重要となります。
効果的な換気のタイミングと方法
具体的な方法は、以下の通りです。

ひとつずつ見ていきます。
1.常に換気を意識する
制作中は窓を開けて、空気を入れ替えることが重要です。
冬場など寒い日は少ししんどいですが、ほんの少し・・・5cmくらいでも窓を開けて作業することをおすすめします。

風邪ひかんよう
たくさん着こまんとな。
扇風機やサーキュレーターで空気の流れを作るとより効果的です。
2.空気の入口と出口を作る
部屋に窓が1つしかない場合、換気の効果が本当にあるのか心配になりますよね。
その場合、玄関や室内ドアを開放して「風の通り道」を作りましょう。
風の通り道によって、空気の循環が更に期待できます。
3.制作後も30分以上換気
描き終わってすぐに閉め切ってしまうのは、まだ滞留している空気があるのでおすすめしません。
最低でも30分は換気を続けて、においをすべて外に出しましょう。
室内環境の工夫
空気清浄機があると、より安心です。
予算に余裕があれば、導入するに越したことはないです。
VOC対応フィルター付きなら、におい成分もある程度除去できて、安心感も高いです。
無臭・低臭のおすすめ画材紹介
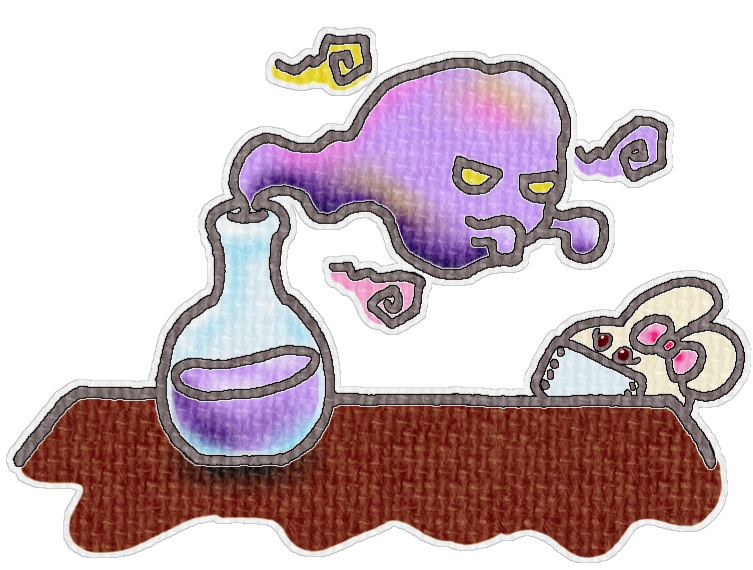
実は、油絵の画材には、においを抑えた「無臭」「低臭」タイプの画材があるんです。
管理人も使用したことがある商品も含めて、いくつか紹介していきます。
無臭・低臭の揮発性油
オドレスペトロール
通常のぺトロールの、においを取り除いた商品です。
においはほぼしないため、室内でも使いやすいです◎
ゼファ ライトアロマペインティングオイル
大手画材メーカーであるクサカベさんのゼファシリーズの商品です。
特徴は、においが微香、天然オイル配合のペインティングオイルです。
普通のペインティングオイルとは違って、さわやかな香りがします。

オイルが入ってる瓶が
透明な濃いブルーなんです。
見た目までおしゃれです。
オイルを薄める時は、オドレスぺトロールを使用します。
そうでないと、せっかく抑えられたにおいが普通にするようになってしまうからです。
その他の無臭・低臭の画材
無臭ペインティングオイル
ペインティングオイルは、調合溶き油です。
メーカーごとに揮発性油や乾性油などを混ぜて、描き心地や絵具が乾燥した時のツヤ感などを調整したオイルとなります。

調味料を混ぜ合わせた
調合調味料みたいなもんやな。
調合する揮発性油の種類にオドレスぺトロールなどを使用してるので、通常のペインティングオイルと比べてにおいは少ないです。
無臭ブラシクリーナー
使い終わった筆を洗う時に使う筆洗液。
無臭タイプはにおいがだいぶ抑えられています。
同じメーカーの無臭タイプと通常タイプを使ったことがありますが、通常タイプは石油のようなにおいです。
蓋を開けた瞬間からにおいが周辺に漂います。

苦手な人にはキツイわな。

管理人は
油絵画材のにおいには無頓着なのですが、
家族からにおいを指摘されてからは
画材はなるべくオドレスタイプで
そろえるようにしています。
それでも「においが無理!」という方にはアクリル絵具がおすすめ
においを気にする声も多く、現代ではさまざまなにおい対策がされた商品が市販されています。

開発してくださる皆さま、
本当にありがとうございます・・・!
しかし、優秀な無臭・低臭な商品とはいっても、完全ににおいがゼロなわけではありません。
出来る限りの対策をして、それでもやっぱりにおいが無理な方もいらっしゃると思います。
その場合は、使用する画材をアクリル絵具に変更するのもひとつの手です。
近年では、アクリル絵具でも油絵風な表現をすることが可能ですし、アクリル画材は片付けも水洗いで簡単に出来ますので、気軽にトライすることが可能です。
「どうしても油絵具で描きたい・・・!」というわけではないならば、ぜひアクリル画材を試してみてください◎
まとめ|におい対策をしながら快適に油絵を楽しもう
油絵のにおい問題は、ほんの少しの工夫で大幅に軽減できます。
- においの原因を知る
- 制作環境の換気を徹底する
- 無臭・低臭タイプの画材を選ぶ
「においがイヤだから油絵は無理・・・!」と感じている方も、今日からできる対策を取り入れれば、油絵をトライできるかもしれません。
ぜひ自分に合った方法を試して、においに悩まされない油絵ライフを手に入れてください◎

最後までお読みいただき
ありがとうございました!
【初心者向け油絵シリーズ】では、画材の選びかたや描きかたを解説しています!
ぜひあわせてチェックしてみてください